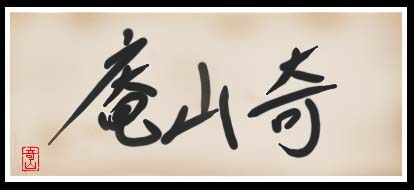
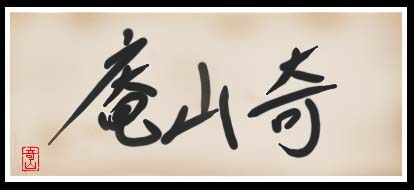
数寄の間
* この部屋では、模型制作初心者・三木が自分の作例等を紹介します。
第2回 「Me262A−2a」作品紹介。
今年(2002年)4月に制作をお願いした「メッサーシュミット Me262 A−2a
w/ケッテンクラート(タミヤ・1/48スケールモデル)」の完成品を受け取ったので、
この場で御紹介いたします。作品を制作してくださったのは、大学のサークルの
先輩です。 デジカメの画像データ容量無変換の大判写真にてお楽しみください。

1.左前方からのショット。上下の塗り分けの境界はモットリング迷彩という
ぼかし塗装が再現されています。フリーハンドのため、技術とセンスが要求される
作業です。 背景に置いたのは空モデラーのバイブル?、航空機模型専門誌の
「Scale Aviation(大日本絵画) Vol.8」です。 ドイツ空軍機特集号。

2.同じ方向から、アップであおり気味にマクロ接写(5cmくらい)撮影。
実機を人間が地面から見上げると、丁度このような見え方になると思います。
機首の機銃点検パネルが浮いて段差が出来ていますが、接着しないで取り外し
可能な状態にして組んでもらった為で、工作ミスに由来するものではありません。
キャノピーも接着していませんが、こちらは合いが良くて、乗せてあるだけでも
ほとんど違和感なく仕上がっています。
前脚柱の伸縮部分は、実機の金属地肌をプラスチックのパーツにアルミ箔を
巻くことで再現してあります。やはり金属色の塗装よりもリアルになりますね。
機体の全面に打たれているリベット孔も手作業で表現していますが、これぐらい
のアップ画像だと工作の細かさが良く分かると思います。スケールモデルの場合
はリベットを省略して構わない(近づかないと見えない部分だから)という考え方も
ありますが、細部にまで手を入れることは存在感を格段に高めると思います。

3.キャノピーを外してコックピット内部を撮影しました。
計器盤、艤装品ともデカールではなく、筆で色を塗り分けています。 銀塗装
はドライブラシの技法を使っていると思いますが、実物は本物と見間違うような
恐ろしい仕上がり・・・(笑)
ここには写っていないんですが、座席のベルトは切ったマスキングテープと丸めた
真鍮線で自作されています。 作り方を教わったので自分もシートベルトは同じ
やり方で作っています。大戦機は実物もシンプルなので、エッチングパーツに
頼らなくても結構いい感じに再現できます。

4.斜め後ろからのショット。
この角度もMe262の精悍さが感じられて自分的にお気にですね。 機体上部の
ループアンテナは、キット付属のブラパーツに代えて真鍮線を使用してあります。

5.主脚収納部のアップ。
パイプ・配線コード類は全て追加工作で再現したもの! 自分、実はこの部分に一番
感激しました。完成してからはなかなか見えない所なので、アッサリ終わらせても苦情は
(たぶん)来ないんですが、ディスプレイで下に鏡を置きたいような出来になっています。


6.7.真横から撮影したものを2枚まとめて。
本機の端正なシルエットを堪能してください。ピトー管が下に曲がっていますが
プラモの急所なので御容赦を・・・(焦)。 実物、まだグラグラしています。

8.俯瞰のショット。
人の目線だと、飛行機を上から撮るケースというのはそれほど多くないので
このような角度は模型々々しちゃってるようで好みではないんですが・・・。

9.正面からアップで。
Me262のオムスピ型胴体も、実はあまり好みでなかったりする・・・。
この機体を大いに気に入っていたというヒトラーはどうだったんでしょう?
ドイツ機ファンからもこの点について真っ向からの批判って聞かないんですよね。
平べったい正面がキライって、もしかして少数意見?

10.真上から平面図っぽく撮影しました。
主翼は胴体と異なり、直線的にハッキリ塗り分けたスプリッター迷彩で塗装して
もらいましたので是非見比べてください。これは実機を再現する塗装指示図に
のっとっていますが、実際のところ迷彩効果に違いはあったんでしょうか?
以上、第2回 「Me262A−2a」作品紹介でした。